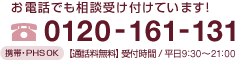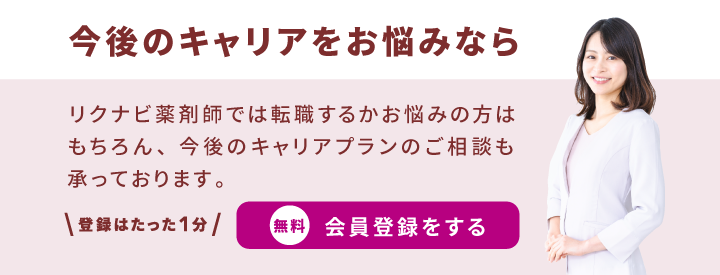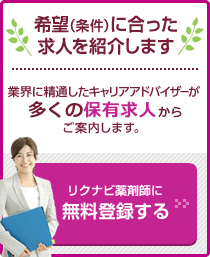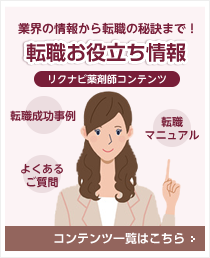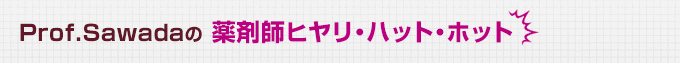
フェブリク錠が初回から20mg/日で処方されていた
最近来局するようになった患者に、病院の循環器内科から初めてフェブリク錠<フェブキソスタット>が処方され、用量が20mg/日であった。患者によると、2ヵ月前に別の内科クリニックでトピロリック錠<トピロキソスタット>が処方されていたが、自己判断で服用していなかった。開始用量が20mg/日となるため疑義照会し、10mg/日に変更となった。
<処方1>70歳代の女性。病院の循環器内科。
| エリキュース錠2.5mg | 2錠 1日2回朝夕食後14日分 |
|---|---|
| ベプリコール錠50mg | 2錠 1日2回朝夕食後14日分 |
| ネキシウムカプセル20mg | 1Cp 1日1回朝食後14日分 |
| フェブリク錠20mg | 1錠 1日1回朝食後14日分 |
<効能効果>
●フェブリク錠10mg・20mg・40mg
痛風、高尿酸血症
がん化学療法に伴う高尿酸血症
患者は約1ヵ月前に初めて来局した。病院の循環器内科からエリキュース錠、ネキシウムカプセルが処方されていた。今回も病院の循環器内科からの処方箋を持参し、フェブリク錠などが処方追加されていたため、患者に確認した。
患者:「実は、尿酸値が高いと言われ、内科クリニックで処方されたことがある。尿酸値は不明です。気にならないので飲んでいません」
詳細を確認すると、約2ヵ月前に内科クリニックから尿酸降下薬(トピロリック錠)が14日分処方されたが、服薬していなかったことが判明した。
フェブリク錠の添付文書に基づき(患者には指導箋を見せながら)、フェブリク錠は10mgから開始する薬であり、用量について疑義照会させてほしい旨を患者に話し、病院の循環器内科に問い合わせた。
薬剤師:「フェブリク初回投与とのことですが20mgでよろしいでしょうか?紹介元の内科クリニックからトピロリック錠は2ヵ月前に14日分処方されたのですが、服用されていないそうです。再度確認お願いします」
結果、フェブリク錠20mgからフェブリク錠10mgへ変更となった。
詳細は不明だが、処方医はフェブリク錠の処方経験もあるベテランであるが、フェブリク錠の初回投与について理解していなかった可能性がある。もしくは、紹介元で処方されていたトピロリック錠を患者が継続服薬していると思い込み、開始用量は20mgでよいと判断した可能性もある。
初回来局時(約1ヵ月前)に、患者が持参したお薬手帳を確認し、記載薬の使用目的などを聴取するべきであった。
患者は病識や薬識が低く、処方された薬を服用していなかった。
初回用量から維持用量に増量する医薬品は少なくない。その場合、初回から維持用量となっていれば、他医療機関からの同薬の継続処方であるかどうかを確認し、少しでも疑義があれば処方医への問い合わせは必須である。
フェブリク錠の痛風・高尿酸血症に対する成人の用法・用量は以下である。
通常、成人にはフェブキソスタットとして1日10mgより開始し、1日1回経口投与する。その後は血中尿酸値を確認しながら必要に応じて徐々に増量する。維持量は通常1日1回40mgで、患者の状態に応じて適宜増減するが、最大投与量は1日1回60mgとする。
[国試対策問題]
問題:40歳代の男性。職場の健康診断で尿酸値の異常を指摘され、A病院を受診したところ、血清尿酸値は9.0mg/dLであった。患者は薬物治療を開始することになり、以下の処方箋を持って、B薬局に来局した。B薬局の薬剤師がA病院の処方医に疑義照会する内容として適切なのはどれか。1つ選べ。
(処方箋)
フェブキソスタット錠20mg 1回1錠(1日1錠)1日1回朝食後
1 フェブキソスタット錠の規格を10mg錠に減量してください。
2 フェブキソスタット錠の規格を40mg錠に増量してください。
3 フェブキソスタット錠をアロプリノール錠に変更してください。
4 フェブキソスタット錠をベンズブロマロン錠に変更してください。
5 特に問題はないため、疑義照会する必要はない。
【正答】1
尿酸降下薬による治療初期には、血中尿酸値の急激な低下により痛風関節炎(痛風発作)が誘発されることがあるので、フェブキソスタットの投与は10mgを1日1回から開始し、投与開始から2週間以降に20mgを1日1回、投与開始から6週間以降に40mgを1日1回投与とするなど、徐々に増量する。
*本稿では、全国各地において収集したヒヤリ・ハット・ホット事例について、要因を明確化し、詳細に解析した結果を紹介します。事例の素材を提供していただいた全国の薬剤師の皆様に感謝申し上げます。

澤田教授
四半世紀にわたって医療・介護現場へ高感度のアンテナを張り巡らし、薬剤師の活動の中から新しい発見、ヒヤリ・ハット・ホット事例を収集・解析・評価し、薬剤師や医師などの医療者や患者などの医療消費者へ積極的に発信している。最近は、医薬分業(薬の処方と調剤を分離し、それぞれを医師と薬剤師が分担して行うこと)のメリットを全国民に理解してもらうためにはどのような仕組みとコンテンツが必要かや、医療・介護の分野でDXが進む中で薬剤師はどのような役割を果たすべきかなどを、日々考えている。
薬学者。東京大学薬学部卒業。その後、米国国立衛生研究所研究員、東京大学医学部助教授、九州大学大学院薬学研究院教授、東京大学大学院情報学環教授を経て、現在、東京大学大学院薬学系研究科客員教授。更に、NPO法人 医薬品ライフタイムマネジメントセンター理事長・センター長。著書には「ポケット医薬品集2024」(南山堂,2024年)、「処方せんチェック・ヒヤリハット事例解析 第2集」(じほう,2012年)、「ヒヤリハット事例に学ぶ服薬指導のリスクマネジメント」(日経BP社,2011年)、「処方せんチェック虎の巻」(日経BP社,2009年)、「薬学と社会」(じほう,2001年)、「薬を育てる 薬を学ぶ」(東京大学出版会,2007年)など他多数。
-
- 事例247
- 「初めだけ」を誤解して空打ちをしていなかった患者
-
- 事例245
- ネオキシテープを手首に誤用していた患者
-
- 事例237
- イナビル吸入粉末剤を経鼻吸入しようとした患者
-
- 事例236
- ゼロックス療法なのにカペシタビン錠の処方がない!
-
- 事例235
- 患者の提出忘れ!処方箋は実は2枚つづりだった!
-
- 事例232
- 在宅介入した薬剤師からの情報で生活改善
-
- 事例228
- 薬剤師提案の血中濃度測定でジゴキシン中毒が発覚
-
- 事例223
- 昇圧薬と降圧薬が同時に処方された
-
- 事例219
- 処方せんの用法の記載に問題あり!
-
- 事例218
- オピオイド服用患者、痛みの強い波と眠気から転倒
-
- 事例217
- シクロホスファミド錠の適応外使用
-
- 事例211
- プレドニン錠中止時の漸減を忘れる落とし穴
-
- 事例206
- スタレボ配合錠L100を半錠で調剤できる?
-
- 事例203
- エフピーOD錠とアジレクト錠の併用?
-
- 事例202
- 包数の多い散剤処方に介入して服薬の煩わしさの改善
-
- 事例201
- 点眼薬のみが処方されていた理由
-
- 事例200
- 家族への服用中止の指示は、電話連絡だけでは不十分
-
- 事例199
- 酸化マグネシウム原末が義歯にはさまって効果減弱
-
- 事例197
- 薬名類似による誤処方を発見し疑義照会
-
- 事例196
- 医師の一言『効果の高い薬』で不安になった患者
-
- 事例194
- 認知症患者の服薬状況の把握不足
-
- 事例192
- 患者が自己判断でリリカOD錠の服用を中止
-
- 事例188
- 指導不足によるタリビッド点耳液の不適正使用
-
- 事例187
- 薬の併用による副作用について疑義照会
-
- 事例186
- アロプリノール錠の服薬状況の認識不足
-
- 事例185
- 患者が一包化薬の分包ごと服用していいかと質問
-
- 事例184
- ゼローダ錠の服薬スケジュールに関して疑義照会
-
- 事例183
- イーケプラ錠の不均等処方について疑義照会
-
- 事例182
- レキップCR錠の急激な減量を発見し疑義照会
-
- 事例181
- ニトロペン舌下錠の保管方法に関する服薬指導不足
-
- 事例179
- 処方意図が不明なため疑義照会を検討
-
- 事例177
- 患者のジェネリック医薬品に対する考え方が変化
-
- 事例176
- 知識不足で『レスパイトケア』の意味が分からず
-
- 事例174
- 骨折でドライブスルー利用した患者への配慮不足
-
- 事例173
- 腎臓疾患患者へのアスパラカリウム錠処方を疑義照会
-
- 事例172
- 薬剤師の聞き方で誤解を生んだ疑義照会
-
- 事例170
- 疑義照会にて薬名類似による処方ミスと発覚
-
- 事例169
- キサラタン点眼液 点眼し忘れ時の対応の説明不足
-
- 事例168
- 慢性腎不全患者へのワントラム錠処方を疑義照会
-
- 事例167
- 口腔内の乾燥によるニトロペン舌下錠の溶解遅延
-
- 事例166
- ウルティブロ吸入後のうがいは必要?
-
- 事例165
- 患者の服薬不遵守を察知し、メトグルコ錠の処方変更
-
- 事例162
- フェントステープの使用法と注意すべき点とは?
-
- 事例161
- 個装箱内の残薬に気づかず破棄
-
- 事例158
- 複合要因から後発品の普通錠を徐放錠で誤調剤
-
- 事例157
- 禁忌薬の認識不足で妻が自身への処方薬を夫と共用
-
- 事例155
- テルネリン錠の増量処方を見落とし調剤
-
- 事例154
- プラリア皮下注には天然型のデノタスが必須と勘違い
-
- 事例153
- 患者からの申告がなく緑内障既往歴を把握せずに投薬
-
- 事例150
- 胃全摘患者へのランソプラゾール処方を疑義照会
-
- 事例147
- 中止すべきバイアスピリンを患者が誤って服用
-
- 事例144
- 前回処方年月日を見誤り、的外れな服薬指導
-
- 事例142
- セレスタミンにプレドニン追加でステロイドが重複
-
- 事例141
- セルニルトン服用が花粉症に効くという仮説
-
- 事例139
- 手書きの麻薬処方箋の「(8時」を「18時」と誤読
-
- 事例138
- リパクレオンカプセルの1シート当たりの数に注意
-
- 事例137
- パーキンソン病治療薬による病的賭博の副作用を発見
-
- 事例134
- ムコスタ点眼液UDの副作用の説明不足
-
- 事例131
- 患者の認識と処方内容に違和感を覚え疑義照会
-
- 事例128
- アロマシン錠に関しての患者の理解度の確認不足
-
- 事例124
- 介護者の負担軽減のために服薬ゼリーの使い方を指導
-
- 事例122
- 腎機能が悪くない患者にケイキサレート散が処方
-
- 事例121
- クラビット錠の疑義照会で、偽造処方箋が発覚
-
- 事例120
- ユベラNカプセルなど3剤の継続処方の確認不足
-
- 事例118
- ノルスパンテープの貼付期間の説明不足
-
- 事例111
- 高用量ベネットによる副作用の認識不足
-
- 事例109
- 水痘患者への亜鉛華単軟膏の処方を疑義照会
-
- 事例107
- 端数のPTPシートを組み合わせて調剤
-
- 事例105
- フォルテオ保管方法の説明不足
-
- 事例104
- 腎機能低下者に通常用量でシタグリプチンが処方
-
- 事例102
- 患児の外見と記載の体重に違和感を覚え疑義照会
-
- 事例101
- ナウゼリンの1回量過量の見逃し
-
- 事例98
- 異なるPTPシートによる数量の誤調剤
-
- 事例97
- 漢方薬初回処方患者への副作用の説明不足
-
- 事例96
- 視覚障害者に最適なうがい液へ疑義照会
-
- 事例95
- 1回量と1日量を読み違えて誤調剤
-
- 事例89
- スタチンの一般名を病院外来事務職員が誤認
-
- 事例76
- 一部手書きの処方箋により用法を誤認識
-
- 事例64
- 服用時点の押印ミスで朝夕の薬を逆に投薬
-
- 事例60
- 患者が激怒!了承を得ずに行った疑義照会
-
- 事例37
- シプロキサンとルボックスは併用禁忌?
-
- 事例14
- インスリン製剤はどれも同じと思った患者
-
- 事例10
- 遮光が必要なのはモーラステープ?
-
- 事例06
- 手書き処方せんを読み間違って半量を調剤
-
- 事例01
- え!?…私ってうつ病?