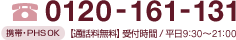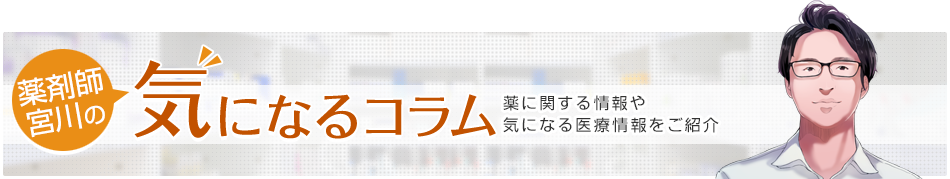2024年10月から新たな制度である「長期収載品に関する選定療養制度」が始まりました。薬剤師の中でもしっかりと理解しきれていないため、患者さんの理解が得られるような上手な説明ができていないという方がいらっしゃるようです。今回はこの新制度について見ていきましょう。
そもそも選定療養とは?
今回初めて聞いた方が多い言葉である「選定療養」ですが、実は以前よりすでに存在しています。元々選定療養とは、「社会保険に加入している患者さんが、保険適用外の治療などに関して、追加費用を支払うことで受けることができるという医療サービス」で、保険外併用療養費制度(健康保険法で規定)に基づいたものです。
具体例を挙げると、差額のベッド代を支払うことによる入院時の個室利用、紹介状なしの大病院受診、差額を支払うことによる歯科治療における金属材料の適応、精子の凍結および融解などがあります。よく医療ドラマで、お金持ちのVIP患者さんが差額のお金を払って個室で入院するというシーンがあると思いますが、あれがまさにこの制度によるものです。
似たような概念である混合診療との違いとは?
選定療養の説明を読んだ方の中で、混合診療とどう違うのか分からないと思った方も少なくないでしょう。選定療養については、混合診療の例外的一形態とは言えます。
そもそも混合診療とは、保険診療と保険外診療(いわゆる自由診療)とを併用して行った際には、保険診療部分も含めて全ての金額が自己負担となるものです。ちなみに、健康保険法においては、この混合診療については原則的には禁止されています(例えば、悪い医師によって悪用されるなどすると多くの不具合が生じかねないという危惧があるためなどの理由によります)が、今回紹介する選定療養や評価療養(厚生労働大臣が定めている高度医療技術を用いた療養などで、今後保険診療に入れるべきかを評価する療養制度、先進医療もここに含まれます)が混合診療の例外となり、この2つに関しては、保険診療部分に関してはきちんと保険適応となります。つまり、選定療養は特別な混合診療ということになります。
なお、選定療養や評価療養の拡大を機に、患者さんの利便性や医療選択の多様性確保のために、今後は混合診療全体を解禁してもいいのではという規制緩和の議論も高まっているため、引き続き最新情報には耳を傾けるようにしましょう。
薬局での長期収載品の選定療養とは?
今回新たに「長期収載品の選定療養」が開始され、多くの薬局で対応が必要となりました。この場合の「長期収載品」とは、「後発医薬品が存在している先発医薬品(対象としては全長期収載品の97%の品目)」のことです。今回の制度をまとめると、「患者さんが、後発医薬品がすでに存在している先発医薬品を希望する場合には、先発医薬品と、薬価が最も高い後発医薬品との差額の4分の1は自費となる」となります。ただし、医療上の必要性があると認められる場合、在庫状況等を踏まえて、当該薬局において後発医薬品の提供が困難であり、長期収載品を調剤せざるを得ない場合に関しては、選定療養の対象外となります。後発医薬品の流通が昨今滞っている現状という背景を踏まえた措置になります。
処方箋の様式も変更された?
今回の新たな選定療養制度が稼働するのと同時に、処方箋の様式も変更されました。処方箋内に「変更不可(医療上必要)」欄と「患者希望」欄が設けられました。前者にチェックがあれば選定療養の対象外である一方、後者にチェックがある場合には選定療養の対象となります。どちらにチェックがあるのかを確認することが大事となります。さらに厄介なのが、当面の間は既存の処方箋も使用できる点です。これまでの様式の処方箋の処方欄の中に「医療上必要」や「患者希望」などと記載すれば有効なので、処方箋が旧様式の場合には、調剤前に全体をきちんと確認する必要が出てきます。加えて、今回の新たな選定療養制度については患者さんの多くがおそらく知らないので、薬剤師からきちんと説明することも必要です。選定療養に関しては、患者さんどころか医療者側も知らない人が結構いるものと思います。ぜひ自分でも勉強していただき、選定療養に詳しい専門家の薬剤師になってください。
リクナビ薬剤師では働く薬剤師さんを応援しています。
転職についてお悩みの方は以下のボタンよりご相談ください。