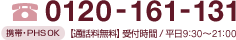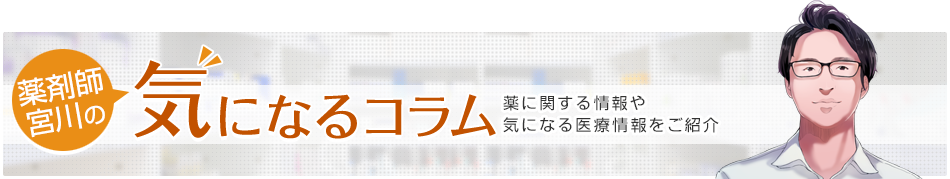あらゆるスポーツに関して誰もが気軽に参加が可能であり、かつ誰でも手軽に観覧できる時代になりました。それに伴い、ドーピングに関する事例も未だに後を絶たないという現状です。より盛り上げたいと焦ってしまいドーピングに手を染めてしまう事例から、意図せず服用していたサプリメントの中に入っていた成分がドーピングになってしまうといった事例など多岐にわたります。
ドーピングの事例に関してはテレビドラマでも題材として取り上げられました(TBSテレビ『オールドルーキー』)。ドーピングはアスリート自身の人生を変えるだけでなく、スポーツの存在意義自体を脅かすことなので、その防止はかなり大事といえます。そうした中で、薬剤師の関与の必要性が増しています。今回はドーピング活動に薬剤師がどのように関与していけるか考えてみましょう。
ドーピングを専門とする薬剤師とは?
以前こちらのコラムでも紹介しましたが、ドーピングを専門とする薬剤師はすでに制度化されていて、人気資格となっています(スポーツファーマシスト:https://rikunabi-yakuzaishi.jp/article/column/sports/)。日本薬剤師会と日本アンチ・ドーピング機構とがタッグを組んでいるものであり、かなり力を入れている認定資格といえます。認定者が増加するに従い、実際のアンチ・ドーピング活動に参画している薬剤師も増えてきました。
ほかでもない筆者自身も同資格を保有しており、アンチ・ドーピング活動には細々とですが参加しております。参加している中で感じるのは、ドーピングは薬物乱用などと密接に関連しており、小さいころからきちんと教えることが重要であるという点です。薬物乱用防止はまさに薬剤師が行うべき社会的活動であり、アンチ・ドーピング活動と一緒に行うことで、より視野も広がり、また、社会的意義も増すといえます。
アンチ・ドーピング活動で一番大事なものとは?
アンチ・ドーピング活動といってもいろいろなものがあります。まず大事なのはアンチ・ドーピング教育と考えます。アスリート自体への教育はもちろん、そのご家族や監督などへの教育も大事になります。いくらアスリート自身が気を付けていても周りの協力がなければ無意味なものとなるからです。加えて、アスリート向けの医薬品やサプリメントを扱っている業者への教育もやはり大切といえます。
また、可能であれば、スポーツファンの方々への教育もできれば行いたいところです。アスリートはファンによって支えられているという側面もあります。そのファンが正しい知識を持ち、厳しく目を光らせることで、アスリートがドーピングに手を出すことを減らせるのではないでしょうか。実際の教育カリキュラムとして、アスリート自身だけでなく、その周辺の方々にも受講を行わせる団体もあるようです。
さらに実務的な内容は?
いくら教育を行っても、ドーピングに関して正しく検出ができない限りは実効性が伴っていないといえます。こうした観点から、ドーピング検査に関するアドバイスや実際の手法の検証などについてもスポーツファーマシストが行っているという団体もあります。加えて、スポーツファーマシストの中には、例えば大学院に進学することで、ドーピングに関する新規の手法開発などについても積極的に関わっているという方も存在しております。薬剤師は化学物質に関して基礎から応用まで幅広く知識を有しているため、ドーピングに関する研究開発にも積極的に関与することで、今後さらに正確な、かつ迅速な検査手法を生み出せるものと期待されます。
今現在スポーツファーマシストとして認定を受けている方や、これからスポーツファーマシストを取得しようとしている方は、新しいドーピング検出に関する研究ができるようになるまで専門性を高めると、より高度なスポーツファーマシストとして活躍できる可能性が高いので、ぜひ考慮してみてください。
一人でも多くの薬剤師がアンチ・ドーピングに寄与し、社会的にも広く認知されていくことを願っています。
リクナビ薬剤師では働く薬剤師さんを応援しています。
転職についてお悩みの方は以下のボタンよりご相談ください。