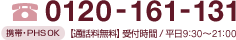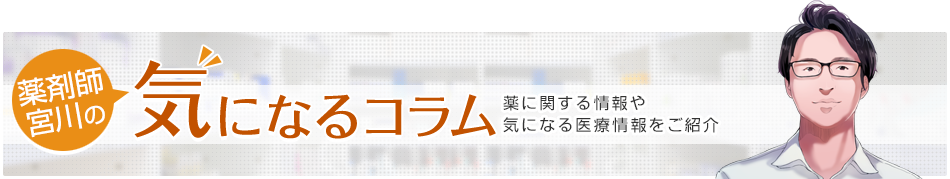薬剤耐性(Antimicrobial resistance; 略してAMR、以下AMRと呼称する)の問題については、以前からずっと指摘されてきてはいますが、現状はさらに懸念されている事項の一つです。今回はAMRについて見ていきましょう。
そもそもAMRとは?
AMRとは、「抗菌薬や抗真菌薬などの病原微生物に対する医薬品の効果が低減する、または無効になってしまう状態」を指します。コロナ禍でも話題となりましたが、特に変異が激しいウイルスで形成されやすいものです。コロナ禍だけでなく、人類の歴史とは、とどのつまり、感染症との戦いの歴史と言っても過言ではありません。
我が国では今でこそがんが死因の第1位ですが、以前は長きにわたって結核が第1位でした。世界的に見ても、過去何度も大規模なパンデミックが起こっており、そのたびに多くの方々が亡くなっています。近年では多くの優れた抗菌薬などの登場により、感染症自体は劇的に減少しました。まさに「人類は大きな武器を手に入れた、まさに人類の宝物である」と表現できると言えます。
しかしながら、その便利さゆえに、乱用が問題となり、誤った使用方法も散見された結果、薬が効かなくなってきているという現状も増加してきています。画期的な新薬が誕生しにくいと言われている昨今において、抗菌剤などでも同様なことが言えます。このような状況は大変問題であり、いずれ人類は感染症で絶滅するとまで予想されているといった有様です。薬のプロである薬剤師としては看過できない問題のはずです。
AMRが生まれやすい状況とは?
前述した乱用や誤った使用方法とはどんなものでしょうか。もちろん安易に処方する医師やそれを見逃す薬剤師がいたとするならば問題と言えますが、実は患者さん側にもAMR形成につながるような要因が潜んでいることが多いのです。
例えば、軽い風邪で病院を受診し、抗菌剤が手元にないと不安という希望を医師に伝えることで処方されたり、医師や薬剤師からの説明を無視して、自分流に抗菌剤を飲んだり(例えば1日3回のものを1日2回で服用したり)、または途中で勝手に中止したり(例えば症状が収まったと自己判断して薬を飲むのをやめたり)と言った場合です。
AMR対策のために薬剤師がすべきこととは?
現実問題として、AMR対策に関して、薬剤師単独では解決が難しく、医師、患者さんとの協調が必要となります。まずはできることを現実的に考えると、軽い風邪の場合には、まずはうがいや手洗いなどの基本的な感染対策をきちんとすることに加えて、OTCでの対処を行うことを推奨する、医師により決められた用法用量を遵守し、たとえ症状が途中で収まっても決まった分はきちんと飲むことを伝えることとなります。
そして、最も危険な場面としては、以前自分がもらった抗菌剤が余っていて、その余りのものを、家族が風邪をひいた際に飲ませてしまうというものです。もちろん薬の知識が皆無な素人が適正な抗菌剤の用法用量を決められるわけはなく、自己判断の量を勝手に決めて与えることによりAMR形成が加速されてしまいます。こういった場面は実は結構多い割には表面化しにくいものでもあるので、薬剤師の方で、手元に余った抗菌剤がないかの確認を毎回きちんとする必要があります。
こういったことは薬局薬剤師だけのことではなく、病院薬剤師でも同様に重要になってきます。なぜかと言うと、もし入院してくる患者さんが以前もらった抗菌剤を持ち込んで、それを入院中に勝手に服用してしまった場合には、本来の治療に支障をきたすだけでなく、病院内でAMRが形成される可能性が高まり、結果として院内感染の温床になるかもしれないからです。閉鎖的な空間である病院の病棟においては、ただでさえ院内感染のリスクが高いので、より重要となってきます。
AMRに関しては、厚生労働省だけでなく、WHOも重要視している事項です。ぜひ人類滅亡を止められる薬剤師を目指してください。
リクナビ薬剤師では働く薬剤師さんを応援しています。
転職についてお悩みの方は以下のボタンよりご相談ください。