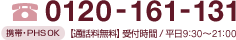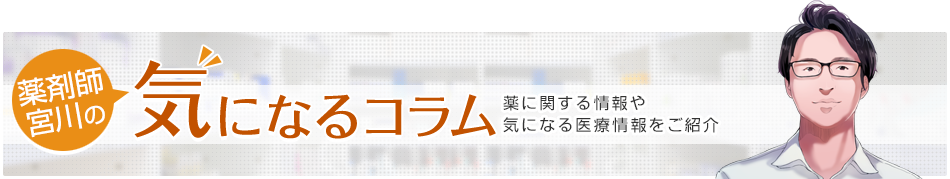医療の多様化がさらにスピードを上げている昨今、他職種連携の重要性が以前よりも増していると言われています。しかしながら、こういう時代だからこそ、最も大事なのは実は病院薬剤師と薬局薬剤師との連携である「薬薬連携」であると考えます。今回は薬薬連携について見ていきましょう。
薬剤師の世界こそ実は他職種だらけ?
一般の方では、薬剤師というとイメージが一つで、「医師の処方箋を受け取って薬を用意してくれる職種」というイメージが強いと思います。もちろん、処方箋に基づく調剤は一部の例外を除いて薬剤師の専売特許であり、イメージとしては間違ってはいません。しかしながら、実は薬剤師と言っても多種多様で、医療業界のど真ん中の薬剤師である病院薬剤師と薬局薬剤師の2つでもまったく異なると言っても過言ではないくらい業務スタイルに距離があるかもしれません。
病院薬剤師は病院に所属する薬剤師のことであり、調剤を基本とすることは事実ですが、近年は病棟やDI業務など病院内の医薬品に関する多岐にわたる業務を担います。他職種と同様、当直ももちろん行いますし、最先端の研究に参画している方もいらっしゃいます。院内のカルテ情報にアプローチできるため、患者さんの疾患情報などをリアルタイムで把握することもできます。また、接する患者さんや疾患も比較的重度であり、扱う医薬品もハイリスク薬が多いです。それゆえに、自ずと身につく知識やスキルも高度なものになり、働きながら取得していく専門・認定薬剤師もがんや感染症などを含めてとても多いです。
他方、薬局薬剤師は調剤薬局(時には調剤併設のドラッグストア)に所属し、病院やクリニックなどから発行された処方箋に基づく調剤、監査、服薬指導を主な業務として、薬を渡した後の経過観察も担います。比較的軽度な患者さんに対応しますが、接する医薬品に関しては病院薬剤師よりも多いという特徴があります。加えて、地域医療の担い手、かつ、病院を退院して自分の家で療養を続けている方に対する薬の専門家という特徴もあるでしょう。病院薬剤師に比べると取得できる専門・認定薬剤師は少ないものの、医療だけでなく、食事や介護などに至るまで理解しているジェネラリストとして成長できるというメリットがあります。このように、病院薬剤師と薬局薬剤師とは、ある意味で薬の専門家としては別の道を歩んでいると言えます。
薬薬連携の必要性とは?
前述したように専門性を高める方向の病院薬剤師とジェネラリストとして力をつけていく薬局薬剤師の間では、以前より少し距離感がありました。一部の例ではありますが、病院薬剤師が薬局薬剤師を専門性の点で下に見ていたり、逆に薬局薬剤師が病院薬剤師のことを、ハイリスク薬以外の薬を知らないと批判したりするといったこともありました。しかしながら、医療が進歩してきた現在においては、両者による連携がより必要となってきているのです。
例えば、がん患者さんにおいては、病院に入院して、ある程度治療をした後は、退院して仕事を継続しながら、外来で抗がん剤治療を継続という際に、抗がん剤の注射剤に精通している病院薬剤師の知識と抗がん剤の内服薬に精通している薬局薬剤師の各々の専門性が交じり合ってこそ、その患者さんの経過観察を入院から退院後まできちんと行えるということが言えます。
さらに考えると、人工知能が医療に参入してきた中で、法令の問題という一面を除けば、調剤業務が代替可能とも考えられていますが、薬薬連携によって各々の専門性を掛け合わせることで人工知能にも負けない体制を築けると考えられます。
なぜ人工知能にも負けないのか?
患者さんの状態というものは、たとえ同じ疾患を抱えていらっしゃっても千差万別であり、さらに刻一刻と変わっていきます。入院時に回復しても退院後に悪化したり、また、その逆もあります。こういう状況を、過去のデータをベースに回帰分析を行うことで将来予測を行うことが基盤となっている人工知能システムが完璧に判断して管理するのは不可能です。こういう個別具体的な状況判断は専門性を持った人にしかできません。
そういう意味で、スペシャリストである病院薬剤師とジェネラリストである薬局薬剤師の両者が存在する薬剤師という職種は、1つずつではもしかしたら人工知能に置き換わってしまうかもしれませんが、2つがタッグを組めば、実は人工知能にも決して負けないのではないかと感じています。病院薬剤師、薬局薬剤師双方とも、これまで以上にお互いを認め合い、きちんと連携できる時代が来てくれたらと願います。
リクナビ薬剤師では働く薬剤師さんを応援しています。
転職についてお悩みの方は以下のボタンよりご相談ください。