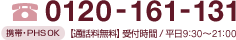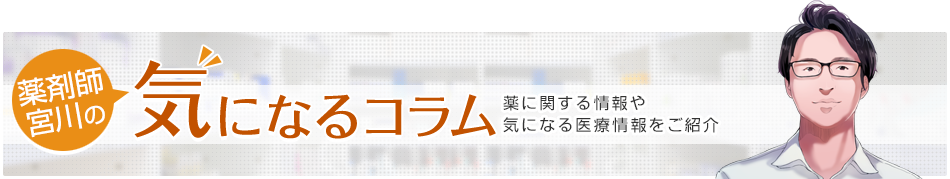メディア等ですでに報道されている通り、日本を代表する大きな国立大学である東京工業大学と東京医科歯科大学の両校が歴史的合併を行って、新しい理系総合国立大学である東京科学大学(略称はScience Tokyo)が誕生しました。理工系の大手大学と医歯学系の大手大学が合併したということで注目されています。筆者はまさにこの合併業務を担当しました。実はこの誕生劇が薬剤師にも波及する可能性が高いのです。今回は東京科学大学誕生と薬剤師との関係について見ていきましょう。
合併前の状況とは?
薬剤師にとっては、病院を学内に持つ東京医科歯科大学は割と身近であったと思います。東京医科歯科大学病院に関しては実際の臨床レベルもかなり高く、コロナ禍においても、東京都でコロナ患者を一番積極的に受け入れた大学病院としても有名になりました。その一方、東京工業大学に関しては、東京にいない方だと、ひょっとすると名前すらも知らなかったかもしれません。
実は研究レベルでは世界的に見ても、両校ともかなりのハイレベルであり、研究者の世界では同等の知名度を持っていました。しかしながら、理工系のトップ大学と医歯学系のトップ大学にもかかわらず、共同研究に関してはあまり多くはないといった状況でした。
合併によって何が起こる?
理工系と医歯学系のトップ大学同士の合併により、世界レベルでの「医工連携」の研究開発推進が期待されています。実際に、合併によって誕生した東京科学大学病院の中に、「医療工学研究所」が設置されることも決まっています。合併直前においても、両校の間で医工連携の共同研究が少しずつ始まってきましたが、その中核拠点が本格的に誕生することで、さらなる躍進が期待できます。また、この研究所には、研究者だけでなく、製薬企業や電機メーカーなどの技術者らも所属する予定です。研究から実際の実用化まで行える場所になるでしょう。
医工連携の重要性って?
ちょっと古い話になりますが、以前『JIN-仁-』という医療ドラマが話題となりました。現代の外科医が江戸時代にタイムスリップして、医療技術が発達していない中でさまざまな医療問題に立ち向かうというものです。その中で、医療技術、医薬品、医療器具などが発達していない中で医療行為を行うのに限界を感じて、己の無力さを痛感する場面で、主人公が「これまで手術を成功させてきたのは俺の腕じゃなかったんだよ。今まで誰かが作ってきてくれた薬や技術、設備や知識だったんだ。そんなものをなくした俺は、痛みの少ない縫い方一つ知らないヤブだった。14年も医者をやって俺はそんなことを知らなかった。自分がこんなちっぽけだってことを、俺は知らなかった」とつぶやくシーンがあります。
まさにこれが医工連携の原点です。医療が進歩してきたのは、まさに工学の進歩があったからにほかなりません。診断装置も治療装置も驚くほど進化してきたことで、医療というものが進化してきました。新薬を創るのにも、その合成装置などの進化が無視できません。つまり、医工連携に重点を置く東京科学大学の理念は、まさに医療の進歩と重なると言えます。
東京科学大学の医工連携で特に重点が置かれていることは?
医工連携の中で特に重点を置かれているのは、なかなか新薬が生まれていないと言われている現状打破です。具体的には、以前より使用されてきた小分子医薬と近年実用化が著しい抗体医薬などの大分子医薬の中間に位置する次世代の医薬品であるペプチド・核酸を用いた中分子医薬の研究開発推進です。
この中分子医薬に関しては、細胞内に容易に入っていくという小分子医薬の利点と、特異的な標的に作用するという大分子医薬の利点とを併せ持つ、大変利便性が高いものです。がんや認知症などの社会問題になっている幅広い疾患に適用できることから、この創出が医療の世界を劇的に変えると言われています。
薬剤師が知っておいた方が良いこととは?
これまでとはまったく異なる医薬品が登場して、これまでの既存の医薬品と置き換わっていくという状況が予想される中で、薬剤師も次世代の知識を積極的に身に付けておかないと生き残っていけないということになります。製薬企業にいらっしゃる方、病院薬剤師はもちろんのこと、薬局薬剤師にも求められます。中分子医薬の基礎となる最先端の分子生物学の知識をこれまで以上に勉強すると良いでしょう。
まずは一般向けの書籍から開始すると、そこには核酸医薬などの内容も大概書かれているので有益です。薬剤師であれば、できれば大学レベルの分子生物学のテキストまでは制覇しておきましょう。加えて、これまでの医薬品に関するメカニズムの深い理解にもつながって一石二鳥です。ぜひ次世代薬剤師を一日でも早く目指し始めてください。
リクナビ薬剤師では働く薬剤師さんを応援しています。
転職についてお悩みの方は以下のボタンよりご相談ください。