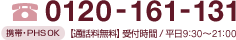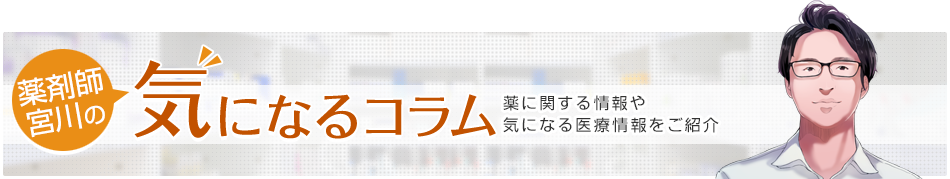薬剤師はもちろん、医療関係者でなくても知らない方がいないと言っても過言ではないステロイド。今回はステロイドについて歴史を振り返りながら見ていきましょう。
ステロイドの発見は実はかなり画期的であった?
皮膚科などを中心として鎮痛や抗炎症などの目的で使用されているステロイドですが、そもそも我々の体に存在している物質を利用したものです。そして、意外と知られていませんが、半世紀ほど昔に、このステロイドの発見に貢献した研究者にはノーベル生理学賞が授与されています。つまり当時は画期的であったわけです。
ステロイド発見に秘められた歴史とは?
ステロイド発見と実用化の歴史には、熾烈な研究者同士の争いがありました。ステロイドの効果を発見したのはハートマンという研究者です。彼は皮膚が黒褐色になっていずれは死に至るという「アジソン病」という重度の疾患に対して、ウシの副腎皮質抽出物が有効であるということを発見して、この抽出物を「コルチン」と名付けました。この時点では抽出物中のどの物質が効果を示しているかは不明でした。
その後、ケンダルという研究者が、このコルチンから8種類の物質を抽出した後に、一つ一つ念入りに生理作用を調べていき、動物に対する延命効果を持つ物質を同定して、「化合物E(後にコルチゾンと命名)」と名付けました。
時を同じくして、ライヒシュタインという研究者によって、同様にして副腎皮質より、29種類のホルモンが単離されて、それらの構造が解明されていました。この29種類の中には、奇しくもケンダルが発見した化合物Eも含まれていました。研究者同士の競争が起こっていたのです。
その後臨床応用への道が開かれた!
前述したように、研究者間での熾烈な競争が繰り広げられていたころ、ヘンチという医師が化合物Eに注目し始めます。リウマチ性関節炎の臨床や研究に携わっていた彼は、妊婦さんや黄疸患者さんではリウマチ性関節炎が軽快することに注目していました。その鍵を握るのが化合物Eなのではないかと考えたヘンチは、ケンダルのもとを訪れて、化合物Eを分けて臨床試験をやらせてくれるように頼みます。
当時すでに製薬企業を巻き込むことで、大量合成に成功していたケンダルは、ヘンチの依頼を快諾して、そこから一気に臨床応用が進んでいきました。化合物Eを投与されたリウマチ性関節炎の患者さんの症状は劇的に良くなることが判明して、当時から難治性の疾患であったリウマチ性関節炎の特効薬としての地位を確立するまでに至ります。ご存じのように、今では多くの疾患で使用されています。
ステロイドについての誤解を解けるようになろう!
前述したように、科学者の手によって研究されてきたステロイドで、かつ使用の歴史もそれなりに重ねてきているため、正しく使用することのメリットが大きいです。しかしながら、多くの誤解を持たれている患者さんが多いのは事実です(下手をすると医療従事者にもいらっしゃいます)。もちろん不適正使用の場合や、内服や点滴で長期間にわたって体内に投与する場合などでは副作用が出ることも少なくないです。薬のプロである薬剤師であれば、その誤解をきちんと解けるようにしたいものです。よく見る誤解としては、
(1)体内に残存することで癖になる
(2)皮膚が黒くなる
(3)顔が赤く丸くなる
(4)骨がもろくなる
になります。
(1)に関しては、ステロイドの外用薬ではまずないと考えられます。症状経過をきちんと観察し、適切に減らしていくことでさらにそのリスクは下がります。
(2)に関しては、ステロイドの外用薬によって黒くなることはまずありません。ただし、皮膚の状態が回復していく中で一時的に黒くなったり、その外用薬に入っている添加物によって日焼けが起こりやすくなるなどはあります。
(3)に関しては、これは大量かつ長期間に使用する(特に内服や点滴での投与)と確かに可能性は出てきますが、ステロイドの外用薬を適切に使用している限りはまず大丈夫です。
(4)としては、これも(3)と同様になります。
つまり、一番多いであろうステロイドの外用薬を使用するという状況では、誤解されている事柄はどれもほぼ起きないと言ってもいいでしょう。ただし、例えば、手に塗るために使用するものを顔に勝手に使用したり、ある方に適切なものをほかの方が勝手に使用したりすることで、副作用のリスクが上がります。
歴史を振り返ると、貴重な薬の一つと言えます。ぜひ「ステロイドの番人」を目指してみてください。
リクナビ薬剤師では働く薬剤師さんを応援しています。
転職についてお悩みの方は以下のボタンよりご相談ください。