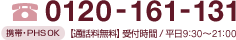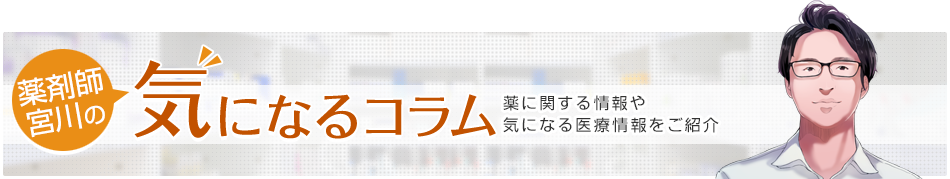超高齢社会やコロナ禍を経験した我が国では、健康志向がこれまで以上に高まってきています。そうした中で、処方箋なしでも購入できる一般用医薬品の種類もどんどん増えてきています。薬剤師がどのような役割を果たせるのでしょうか。今回はセルフメディケーション支援の観点から考えてみましょう。
セルフメディケーションの現状は?
医療用医薬品から一般用医薬品へと転換された「スイッチOTC」に関しては近年急速に増えてきています。最近でも胃薬で登場しています。こういった医薬品は薬剤師にしか販売が許されていないため、薬剤師が必ず常駐している調剤薬局(もしくは調剤併設のドラッグストア)で積極的に販売されています。しかしながら、未だに大部分の一般用医薬品が第二類医薬品、第三類医薬品ということもあり、実際の現場においては、一般用医薬品販売の主力を登録販売者が担っているという場面も少なくありません。
つまり、「薬剤師は処方箋による調剤をメインに、一般用医薬品販売は登録販売者が大部分を担っている」という現実があります。こういった背景から、セルフメディケーションの知識に関しては、登録販売者の方が実は詳しいという状況も見られます。筆者自身もこれまで多くの薬局を実際に見てきていますが、ベテランの登録販売者の方が現場でセルフメディケーションの専門家として活躍しているという場面を多く見てきました。むしろ薬剤師が教えてもらうということもありました。しかしながら、今後はもっと薬剤師がセルフメディケーションに積極的に関与した方がいいと感じています。
今後のセルフメディケーションの在り方とは?
メディアでも毎日のように見かけることですが、現在多くの病院が赤字経営となっています。また、優秀な医師ほど、若いうちから高給を狙って美容外科へと進むといういわゆる「直美問題」も問題視されています。国民皆保険制度自体はそう簡単には崩壊しないことが予想されるものの、今後の医療の在り方は変わってくるものと感じています。
アメリカなどのように皆保険制度がない国のように、簡単な症状であればまずはドラッグストア・薬局へという流れが加速すると思います。現に、薬局薬剤師の方からも、「最近は処方薬以外の健康相談が増えた」、「咳などの簡単な症状の場合にはまずは一般用医薬品を買いに来る方が増えている」などという意見も聞くようになりました。調剤を独占業務とする薬剤師にとっては、もちろん医療用医薬品の知識は大事なのは確かですが、今後は、服薬指導の際に、今処方されている薬以外の健康相談への的確な回答ができる能力なども求められてくると考えられます。
薬剤師が今後セルフメディケーション推進のためにやるべきことは?
具体的に考えてみたいと思います。薬局というのは病院以上に地域医療を担っている場所と言えます。気軽に立ち寄れて、気軽に相談できる、そういった場所であることは明白です。
例えば、薬剤師と登録販売者がタッグを組んで、地域の方への「健康教室」などの勉強会を提供するということが考えられます。専門性を上げていくという医療業界の流れもあり、薬剤師の中にも多くの専門・認定薬剤師があり、実際にいくつか取得している方も多いかと思います。その専門に関する教室であれば、自身の専門性をさらに発揮できるという点で有効です。
また、登録販売者資格取得者のキャリアは思っている以上に多種多様で、栄養士資格を持っている方、看護師資格を持っている方、料理人だった方、はたまたミュージシャンだった方などがいらっしゃいます。こういったキャリアと関連した話を取り入れることで、より幅広い視点から教室を展開できることでしょう。
加えて、新しい税制である「セルフメディケーション税制」についての勉強会なども行うと良いでしょう。こういった仕組みについては知らない方が多いので、薬局にある具体的な商品について説明しながら行うとより有効かと思いますし、売り上げアップにもつながるので、売る側と買う側お互いがwin-winになるものと思います。
さらに、災害時には物資配給拠点だけでなく、災害時における健康維持などの情報発信拠点となれるように日ごろから準備しておくことも有益だと思います。
ここで紹介した勉強会を実際に開催している薬局も増えてきていますので、こういった健康教室にさらに何かプラスαの付加価値を加える取り組みができれば先進的な薬局になれるものと思います。
ぜひ自分でも何ができるのか考えてみてください。
リクナビ薬剤師では働く薬剤師さんを応援しています。
転職についてお悩みの方は以下のボタンよりご相談ください。