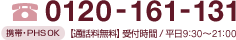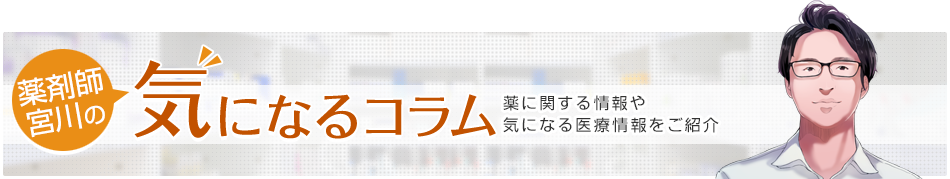薬剤師をやっていると必ず一度は患者さんから質問されることですが、同じ処方箋でも、持っていく薬局によって会計金額が異なってくるのが日本における調剤の仕組みです。質問された際に、正しく答えられないと、どんなに服薬指導が優れていても、結果として患者さんの本当の信頼は得られないとも言えます。今回は金額の違いについて一緒に復習しましょう。
そもそも薬価ってどうやって決まっているの?
調剤で用いられる医薬品に関しては、厚生労働省によって公定価格が決まっていて、価格に関しては全国一律になります(これを薬剤料と呼びます)。ただし、「調剤報酬制度」で定められている事項によって違いが出てきます。この制度で出てくる「調剤報酬」とは、ざっくりとまとめるなら、薬局が患者さんから処方箋を応需して、専門的技能・知識を持った薬剤師によって調剤され、患者さんに渡して、その後薬の管理を続けるという一連の専門的事項に対する手数料という感じです。具体的には次のものが主なものとして規定されています。
(1)調剤技術料
(2)薬学管理料
(3)特定保健医療材料
各々を具体的に見てみるとこんな違いが!
前述した(1)に関しては、「調剤料(医薬品を調剤する技術に関しての費用で、薬の剤形によって異なる)」と「調剤基本料(医薬品の調剤を行うための設備や医薬品の備蓄にかかる費用で、薬局を利用する基本料金みたいなもの)」があります。
なお、調剤基本料に関しては、薬局の立地(門前薬局・門内薬局かそれ以外の薬局か)や規模(どういった処方箋をどのくらい扱っているか)によって変わってきます。この価格でまずは変わってきます。
(2)に関しては、服薬指導や情報提供を行ったり、患者さんの薬歴を記録して管理するための費用です。正式名称としては、「薬剤服用歴管理指導料」と呼ばれるものですが、患者さんの希望によって、特定の薬剤師をかかりつけ薬剤師として指名した場合には、「かかりつけ薬剤師指導料」に変わって、追加費用が発生します。
(3)に関しては、インスリンの自己注射や在宅医療での点滴の針といった医薬品使用のために必要な医療器具に関する費用です。
これらのほかにも、持参する時間帯によっては、時間外加算や休日加算などの加算費用も発生します。地域医療に貢献している体制を取っていて、実績も十分ある薬局の場合には、「地域支援体制加算」を加算していることもあります。加えて、医薬品を選択する際に、どうしても先発医薬品がいいという場合には、選定療養における追加料金が発生したりもします。
会計の違いを考えてみると?
薬局の会計の際に支払う料金の合計は、薬剤料のほかに、前述した各種加算の費用が合わさったものになります。これにより、同じ処方箋であっても、持参する薬局や患者さんの状態などによって多種多様に変わってくる仕組みであることが理解できるかと思います。
加えて、ジェネリック医薬品を選ぶ際に、同じ成分と同じ量のものでもメーカーによって金額が異なることも少なくないため、薬局側が処方箋をぱっと見ただけで正確な会計料金を把握するのは不可能であり、服薬指導時にしか分からないことも多いです。
会計を安くする方法とは?
患者さんから、「どうやったら会計を安くできるのか?」と質問された際にはどう説明するのが良いでしょうか?前述したように、患者さんによって千差万別なので一概には答えられませんが、説明すべきことはあります。具体的には次の事項が例になります。
・お薬手帳を毎回きちんと持参する
・できるだけ薬局は一つにまとめる、かつ、病院やクリニックの近くではなく、自分の住んでいる家に近いところを選ぶ
・無駄な医薬品を減らす
・服薬指導の際に薬剤師に医薬品や健康についていろいろと相談する
要するに、患者さんに会計を安くするような提案について説明すること以上に、追加料金が発生したとしても納得してもらえるような努力を薬剤師や薬局スタッフが一丸となってすべきであるということです。かかりつけ薬剤師がその良い例で、かかりつけ薬剤師になるということは、毎回、追加料金を払って、多少の手間をかけてでも、その患者さんがわざわざ特定の薬剤師に会いに来るわけですから素晴らしいことです。
薬剤師の多くが自分の給与がどこから出ているのかをあまり理解していないと感じています。ぜひ薬剤師各個人が、いろいろな追加費用を払ってでも、処方箋を自分の薬局へ患者さんが持参してくれているということ、そこから自分の給与が出ていることを理解し、その分しっかりと患者さんの期待に応えられるように精進してみてください。
リクナビ薬剤師では働く薬剤師さんを応援しています。
転職についてお悩みの方は以下のボタンよりご相談ください。