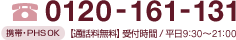新しい細菌やウイルスが生まれる中で、常にワクチンや治療薬の登場が期待されています。その反面、いくら薬が出てきても細菌やウイルスに薬剤耐性ができてしまうかもしれないという懸念は常にあり、人類は薬剤耐性菌や薬剤耐性ウイルスに悩まされ続けてきました。今回は薬剤耐性菌についてみてみましょう。
薬剤耐性菌の歴史は実は古い?
細菌を殺す抗生物質が初めて発見されたのがおよそ100年前なので、薬剤耐性菌の歴史は比較的新しいだろうと思っている方が多いかもしれませんが、実はもっと古いのです。400万年以上前にできた洞窟の中からも薬剤耐性菌は見つかっていて、人が住んでいない場所である北極の永久凍土の中からも見つかっているのです。一部の細菌は抗生物質が見つかる前からすでに薬剤耐性を持っていた可能性があります。
よく考えてみると、例えばペニシリンは、細菌を培養したシャーレの中に混入していた青かびが細菌を溶かしていたことで発見されましたが、かび自体は昔から存在していたものです。このことから、かびの抗生物質成分と細菌との接触には長い歴史があり、その中で耐性を獲得していたものもいたということですね。
ただ、抗生物質が医療に使われ始めた1940年代から薬剤耐性菌の出現数が急速に増えていったのは事実です。メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)を皮切りに、その後、ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)、基質拡張型ベータラクタマーゼ(ESBL)産生腸内細菌科細菌、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌など次から次へと出現してきました。近年では、厄介な細菌である緑膿菌でも多くの薬剤が効かない多剤耐性緑膿菌(MDRP)も出てきており、注意が必要です。
このまま耐性菌が増えてくると、将来は感染症で人類が滅びるとも予測されており、今回の新型コロナウイルスのパンデミックを経験したこともあり、あながち間違った未来予測ではないかもしれませんね。もちろん、薬剤耐性菌自体は普通の細菌と同じで、免疫能がきちんと整っている方では問題にはなりませんが、免疫能が弱まっている方では注意が必要になります。
耐性獲得のメカニズムは?
メカニズムとしては未知の部分が多いのですが、わかっている範囲だと下記のようなメカニズムが報告されています。
(1)細菌の膜を変化させて薬剤を入りにくくする
(2)細菌内に入ってきた薬剤を外へ排出させる
(3)薬剤が作用する部位の構造を変化させて効果が出ないようにする
(4)細菌内に入る前に薬剤を分解する
(5)細菌全体を粘液で覆い、薬剤から身を守る、
いたちごっこにはなりますが、これまでとは違う新しい作用機序の抗生物質を発見したり、また、合成したりすることが今後はさらに必要になってきます。ただ、それ以上に、耐性獲得のメカニズムの研究も今後大事になってくるテーマだと思われます。
薬剤耐性菌を生まないためには?!
一番大事なのは、最近特に言われているように、抗生物質の乱用をやめることです。薬剤師を題材にした話題のマンガである「アンサングシンデレラ」でも、不要な抗生物質を出さないように薬剤師から医師に提言する場面が出てきます。
ただ、医療者側だけの努力ではどうしようもありません。患者さん側でもそういった意識が必要になります。未だに過剰に心配をする患者さんが、医師に無理にお願いして抗生物質を処方してもらうということが少なくないからです。心配になる患者さんは、薬の知識を十分には持っていないのでその気持ちを否定はせず、理解しつつ、薬剤耐性についてきちんと説明することが、まさに今後の薬剤師にとっての重要な使命かと感じます。
また、医療者の中にも勘違いしている人がいるのですが、薬剤耐性菌の中には実は耐性が弱くて、効果が落ちているだけのものもいて、こういった細菌は十分な量の抗生物質なら倒せるのです。そのため、耐性菌の疑いがある患者さんに医師がその該当の薬剤を処方する際に、もしかしたら薬剤感受性の検査をしっかりと行い、十分量なら効果が見込めると判断し、その薬剤を処方したかもしれません。こういった場面に出くわした際には、患者さんに検査の有無、必要となれば処方医にも問い合わせすると良いかもしれません。
さらによく知られているように、5日分処方された場合は、5日分きちんと飲み切ることが必要です。途中で勝手に服用をやめることで、血中濃度が低い状態になってしまい、耐性が生まれやすくなってしまうのです。こう見ると抗生物質が処方された場合には、薬剤師側で注意することは意外と多いですね。ぜひとも薬剤師が、薬剤耐性を食い止める関所となりたいものです。
リクナビ薬剤師では働く薬剤師さんを応援しています。転職についてお悩みの方はこちらのフォームよりご相談ください。