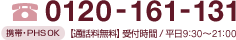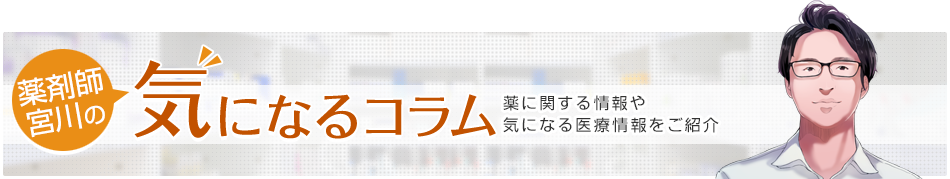新薬が生まれにくくなっている昨今、既存薬を別の疾患へと転用しようというドラッグリポジショニングの研究が加速しています。既存薬の価値の再構築という点でも有意義だと考えられています。以前も本コラムにて紹介しましたが(https://rikunabi-yakuzaishi.jp/article/column/repositioning/)、今回はその最新動向をまとめたいと思います。
これまでのドラッグリポジショニング研究では?
以前のコラムでも触れたことですが、これまでは偶然に発見された副作用を薬の作用として転換していく手法である「偶発的発見型」が主流でしたが、近年は、ゲノム創薬の目覚ましい発展により、作用機序や標的分子の網羅的解析によって新たな効果を発見していく「戦略的導出型」が拡大してきています。
また、ドラッグリポジショニングと似ている概念ですが、ある疾患の薬が別の疾患にも効果を発揮することを利用する手法も広がってきています。それが「ドラッグリパーパシング」です。
薬というのは生体内のある分子や経路に作用するものですが、その分子や経路自体が複数の疾患に関与する場合には、複数の疾患の治療薬となり得るという特徴を利用するものです(例えば、乳がんの抗がん剤を骨粗しょう症の薬へと転用したラロキシフェンなどが該当、今回は便宜上ドラッグリポジショニングに含むことにします)。特に希少疾患や難治性疾患の治療薬の創出に期待されています。
最近のドラッグリポジショニング研究の特徴とは?
近年さまざまな場面でAI(人工知能)という言葉を目にするようになりました。人間の知能により近いレベルのAIも登場してきていることで、以前のAIよりも進化してきています。
医療の中にもAI活用が大いに期待されていて、現にすでにさまざまな場面で実用化への研究が進んでいますが、ドラッグリポジショニングにおいてもAIが大きな武器となると言われています。前述したように、戦略的導出型の手法を取るためには、さまざまな形態のデータを活用する必要があります。このデータはまさにビッグデータであり、これまで人間が行うことには時間的制約などの限界がありました。
ところが、AIを用いることで、時間が大幅に短縮できることに加えて、これまで気が付かなかった側面の特性が可視化されてきたりして、さらに創薬という点では有益な情報が取得できることが注目されています。例えば、既存の薬のあらゆるデータを複数の医療機関から集めて、多変量解析によって一気に分析することができ、得られたデータはかなりの普遍性があり、日本のみならず、世界的にも活用できる可能性が高いものとなるでしょう。
さらに有益な特徴も!
前述したことに加えて、同じ疾患に多剤が使われたりもしますが、違った種類の薬の組み合わせのどれが一番有効で、かつ、どの組み合わせなら他の疾患にも応用可能かなどという、かなり複雑な解析にもAIは適しています。
これまでの人的アプローチ(専門家が論文をたくさん読んで薬のターゲットをしぼりこむという手法)では、時間的制約以上に、その専門家の趣向に依存してしまうこともあり、せっかく有益な情報を取り逃してしまうということも少なくなかったですが、AIではそういったことはありません。
ただし、AIも万能ではなく、特に医学用語や化学物質の名前などといった高度な用語の理解という点では少し劣るため、最終的には専門家によってチェックする必要はあります。まさに「ヒト×AIのコラボ」こそが、これからのドラッグリポジショニングを良い方向に推進していけると思います。そういった側面では、薬剤師も薬の専門家として今後はドラッグリポジショニングにおいて活躍していけるのかもしれません(現に、「薬剤師でデータサイエンス・AIに精通している方急募」という求人も見かけることが増えてきています)。
ドラッグリポジショニングに興味がある薬剤師の方は積極的にAIを使いこなせる知識とスキルを身に付けるとよいでしょう。
薬剤師として決して他人事ではないドラッグリポジショニングの動向については、ぜひ今後もしっかりと注視してみてください。
リクナビ薬剤師では働く薬剤師さんを応援しています。
転職についてお悩みの方は以下のボタンよりご相談ください。