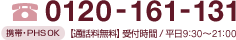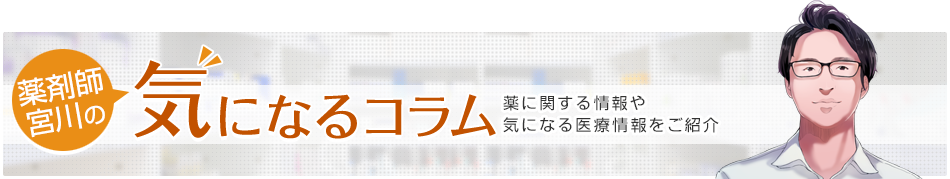超高齢社会に突入した日本において、がん患者がさらに増加していくことが懸念される中、最近話題となっているものとして「がんゲノムプロファイリング検査」があります。一見薬剤師には関係なさそうと思いきや、決してそうではありません。今回はこの検査について見ていきましょう。
これまでの治療とは何が違う?
これまではがん患者さんへの治療といえば、抗がん剤を選ぼうがそうでなかろうが、ほとんど同じような治療法をしていました。治療を始めてみなければ本当の効果などは予測が難しく、効いたり効かなかったり、副作用が起きてしまったりということも少なくありませんでした。近年は、ついにがん患者さんに個別的にアプローチできるようになってきました。このための大きな武器としてがんゲノムプロファイリング検査があるわけです。
どういった検査か?
がん患者さんと一口にいってもその状態は多種多様です。特にがん細胞内の遺伝子変化は複雑なものとなっています。このことが適切な治療法が遂行できない大きな壁となっていました。加えて、検査法も簡便なものとはいえず、多数の遺伝子を調べるためには時間と労力がかなりかかるという状況でした。
ところが、がんゲノムプロファイリング検査においては1回の検査で多数の遺伝子を同時に調べることができて、かつ、時間もかなり短縮されたものとなっています。具体的な流れとしては、手術や生検などで採取したがん組織を処理して、次世代シークエンサーと呼ばれるゲノム情報を高速で、かつ、大量に読むことができる装置で調べます。その後遺伝子変異が見つかり、その遺伝子変異に対して効果が期待できる治療薬があれば、臨床試験でその治療薬の効果を調べるという流れです。
一般的には自費の検査ですが、条件を満たした場合には保険適応可能となります。さらに、最近議論を呼んだ「高額療養費制度(医療費が高額になった場合に一定の金額を超えた分が払い戻しされる制度)」の対象となる場合もあります。
保険適応可能となる条件とは?
まず大前提として、「標準治療がない固形がん患者または局所進行もしくは転移が認められ標準治療が終了となった固形がん患者(終了が見込まれる者を含む。)であって、関連学会の化学療法に関するガイドライン等に基づき、全身状態および臓器機能等から、本検査施行後に化学療法の適応となる可能性が高いと主治医が判断した者に対して実施する場合」というものです。具体的に列挙すると次のようになります。
・全身状態良好
・病理学的診断によって悪性固形腫瘍(固形がん:がんのうち血液を作る臓器である骨髄などから発生する白血病などを除いた、かたまりを作って増殖するタイプのがん)と診断されている
・治療切除不能または再発の病変を有する次の腫瘍
(1)標準治療がない、標準治療が終了している(終了が見込まれる固形がんを含む)
(2)標準治療がない固形がん(原発部位が不明ながんや希少がん) なお、病理学的診断が必要になるなどの条件があるため、どこの病院もがんゲノムプロファイリング検査については病理部もしくは病理部と連携を取っている部署が行うことが多いです。
がん遺伝子検査とどう違う?
似たような検査で「がん遺伝子検査」というものがあります。これは以前より行われてきたものです。名前は似ていますが違う検査です。こちらは、肺がんなどの一部のがんで、医師が必要と判断した場合に、1つ~少数のターゲットとなる遺伝子を調べて診断して、その結果で治療薬を選ぶというものです。この検査はあくまで標準治療内で行われるものです。例えば分子標的薬の選択の場合に使用されています。
遺伝子を調べるという点では同じような感じですが、ゲノムプロファイリング検査の方が多くの遺伝子を一度に調べることが可能、また、標準治療外で行われるという特徴があり、比較すると、「治療の最後の砦」という表現がまさに相応しいかと思います。これまでは治療法がなく放置しかなかったがんへの積極的アプローチという点では画期的なものです。
薬剤師に関係ないのでは?
薬剤師に一見関係ないというふうに思われますが実は違います。確かに多くの場合には臨床検査技師などが主に関わっている検査ですが、病院によっては薬剤師が行う場合もあります。例えば病理部に所属しゲノム研究をしている薬剤師が担っている場合もあります。薬剤師であれば検査後の治療薬の選別まで関われるという大きなメリットがあります。つまり、ゲノムに詳しい薬剤師になれば、こういった検査に関われる可能性が高いです。
また、今後もし在宅医療などで、薬局でこういった検査が法的に可能となった場合にすぐに動けるようになっておくとよいでしょう。まずはゲノムの基礎知識の勉強から始めてみてください。
リクナビ薬剤師では働く薬剤師さんを応援しています。
転職についてお悩みの方は以下のボタンよりご相談ください。