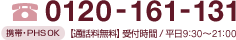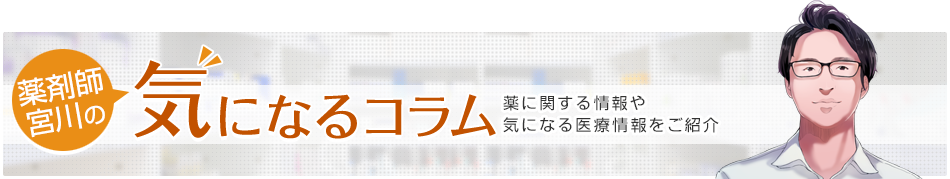近年の医療の高度化・多角化に伴い、他職種連携によるチーム医療がより大事になってきています。薬剤師も例外ではなく、病院においては薬剤師の重要性が増しています。その中で注目されているのが病棟専任薬剤師です。今回は病棟専任薬剤師について見ていきたいと思います。
病棟に薬剤師がいるようになったのはいつか?
そもそも1990年あたりから病院によっては薬剤師を各病棟に配置するという流れはありましたが、一部の大きい病院に限った話でした。しかも調剤業務の合間や終わった後に少しの時間だけ寄るという感じでした。次第に医療が高度化してくる中で、医薬品の種類が多様化してきたことを発端に、病棟に薬剤師を常駐させることが大事だという風潮になってきて、ついに2012年度の診療報酬改定において、「病棟薬剤業務実施加算」が算定要件になったのです。ただし、まだ病院によっては看護師などが病棟の医薬品管理を実質担うなどの現状が続きました。
この現状を打開しようと、2016年度の診療報酬改定で、「病棟薬剤業務実施加算2」が新たに設けられました(2012年度のものを「病棟薬剤業務実施加算1」としています)。これにより、全病棟の専任薬剤師を置くことに加えて、薬剤管理指導業務以外に病棟薬剤業務を週20時間以上実施することが原則として規定されました。また、休日・夜間の対応もできる限り行うこととなっています。ただし、臨床現場の人手不足という側面も加味して、何名かの薬剤師で分担することも可能としています。
近年では全国的にその重要性が認められつつあり、病院によっては各病棟に院内薬局とは別の「サテライトファーマシー」を置き、常駐の専門領域別の薬剤師を置いているという事例もあります。
どういった業務内容になるのか?
病棟業務自体の特徴もあるのですが、病棟専任薬剤師業務はかなり多岐にわたります。病棟に入院していらっしゃる患者さんのところへお邪魔して、医薬品の使用方法や効果などを説明しつつ、副作用歴などを問診することがまずは一番大事な業務になります。ここで得られた情報については随時医師や看護師などと共有することで、チーム医療の一員という感覚も強くなっていきます。
さらに医師の処方提案を行う場面もあり、他の薬剤師業務では得られないやりがいも感じられます。患者さんへの応対だけでなく、医師や看護師向けの薬物療法の講義を行うことも少なくありません。日々増えている新薬に対する専門的見解を持っているのは薬剤師ですので、その立場からほかの医療従事者の教育担当という役割も担います。また外科系の病棟の場合には、手術室に常駐している場合もあり、麻酔薬などの管理を行っているという病院の事例もあります。
さらにこんな業務まで!?
周知の通り、がん患者さんは年々増加しております。その一方で、抗がん剤の進歩も急速なものがあります。以前は入院して行うのが普通だった抗がん剤治療が、今は外来でも行えるようになってきました。入院していた患者さんに対して引き続き外来で治療するという流れになります。
治療後に自宅に帰るというスタイルが定着してきたことで、治療後の経過観察を自分で行わないといけなくなり、治療後の副作用などについて心配される患者さんも増えてきたという背景があります。そのため、大学病院を中心として一部の病院では、がん関連の専門・認定薬剤師を取得した薬剤師が、自身が常駐する病棟に入院していた患者さんに対して、抗がん剤治療に関する面談を行うという薬剤師外来を設けるところも出てきています。
時にはその患者さんのかかりつけ薬局とも連携することで、よりよい治療効果発揮が望めるようになってきています。薬剤師側としても、チーム医療の一員として積極的に関わっているということを理解できて、よりよい業務遂行への熱意が増すという利点もあります。
どこの病院も薬剤師が不足しているため、病棟専任薬剤師に力を入れたくてもなかなかできないというところもあります。薬局薬剤師や今現在従事していないという方々も、ぜひ興味を持ってみてください。
リクナビ薬剤師では働く薬剤師さんを応援しています。
転職についてお悩みの方は以下のボタンよりご相談ください。