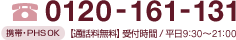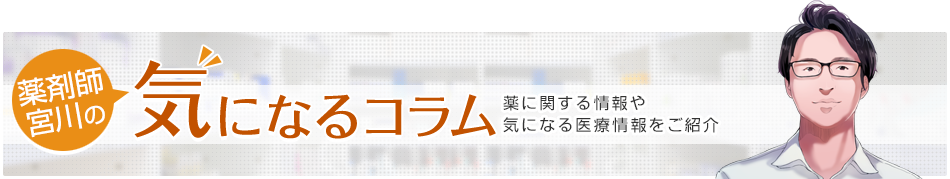医療の高度化によって、薬剤師にも専門性が求められるようになりました。もはや薬剤師資格を持っているだけでは良い待遇は期待できない、そんな時代になってきています。専門性を上げるという取り組みの一つとして認定・専門薬剤師を取得するというものがありますが、新しい制度である「外来がん治療専門薬剤師」が話題となっています。今回はこの資格について見ていきましょう。
これまでのがん関連の薬剤師との違いとは?
がん大国と呼ばれている日本において、これまでもいくつかのがん関連の薬剤師資格が存在してきました。具体的に列挙すると次のような感じです。
(1)がん薬物療法認定薬剤師
(2)がん専門薬剤師
(3)がん指導薬剤師
(4)外来がん治療認定薬剤師
まず(1)に関しては、がん薬物療法のスペシャリストとしての資格であり、適切にがん薬物療法が行えるようにサポートする専門家です。
(2)に関しては、(1)と同様、がん薬物療法のスペシャリストですが、こちらの方がより高度な知識を有する専門家であり、患者さんへの薬物管理指導においても中心的な役割を果たします。実際に、(1)と比べると、学会発表や研究活動も必要となり、研究者としての1面も持っているという特徴もあります。
(3)に関しては、(2)の資格を取得して5年以上という要件も加わるさらに高度な専門家で、がん専門薬剤師などに対して指導を行える講師的なポジションを担います。
(4)に関しては、今回紹介する新たな専門薬剤師の基礎となるものです。この(4)が発展して生まれたのが今回紹介する「外来がん治療専門薬剤師」になります。主に、がん薬物療法のうち、「外来(つまり通院)」において行われるもののスペシャリストとしての資格です。この(4)を取得しなければ、今回の資格を取得することができないため、まずは(4)の取得を目指すということになります。
なお、(1)、(2)、(3)に関しては、薬局薬剤師ではかなりハードルが高く、実質病院薬剤師、特に大学病院など高度な医療を提供している病院に所属する薬剤師でなければ取得できなかったのですが、(4)と「外来がん治療専門薬剤師」に関しては、薬局薬剤師でも取得することが現実的に可能となるという点も注目すべきことかと思います。それだけ、がん薬物療法に関しては、外来においてという場面が増えてきたとも言えます。
どうやって取得するのか?
前述したように、「外来がん治療認定薬剤師(略称APACC)」を取得してからというのが原則です。ちなみに、「外来がん治療専門薬剤師」の通称はBPACCになり、明確に区別されています。
具体的には、まずは、日本臨床腫瘍薬学会が認定している講習会・研修会などに参加して必要な単位数を取得します。業務従事年数3年以上が必要となりますが、その間に、外来でのがん薬物療法に関する症例を10症例提出しなければなりません。これらの要件を満たした後に、学会が実施する認定試験(書類審査、筆記試験、面接試験)に合格することで、ようやく外来がん治療認定薬剤師を取得できるという流れになります。
その後、外来がん治療専門薬剤師を目指すことになりますが、実務経験は5年以上が必要となるため、追加で実務経験を数年積む必要がある方も出てきます。さらに、日本臨床腫瘍薬学会が行うがん診療病院連携研修を修了することも必要です。薬局薬剤師の場合にはこのルートになりますが、病院薬剤師の場合には、病院での勤務歴などによっては研修を修了したと同等とみなされることがあります。いずれにしろ、比較的ハードルは高いですが、日々外来がん薬物療法の業務に従事していれば、乗り越えられない壁ではないと考えられます。
活躍の場は広がっていく?
近年、がん薬物療法の在り方が以前と比べてがらっと変わってきています。以前は入院してベッドの上で注射によって抗がん剤などを投与するという場面が多かったですが、最近では、日常生活を送り、仕事を続けながら治療を続けるという風潮になってきました。それにより、外来で抗がん剤などの治療を受けているという方が増えてきました。
適切な薬物療法を遂行するためには、患者さんの服薬状況を常にきちんとモニタリングすることが必須です。特に抗がん剤は継続しないと意味をなさないものも多いので特に大事です。こういった重要な局面に、今回の「外来がん治療専門薬剤師」資格取得者が活躍できるものと思います。実際に病院などでがん薬物療法に関する外来を置いているところもあるので、そういったところでも活躍できるでしょう。今後もがん患者さんは増えていくことが予想されているので、ぜひ取得を目指してみてください。
リクナビ薬剤師では働く薬剤師さんを応援しています。
転職についてお悩みの方は以下のボタンよりご相談ください。