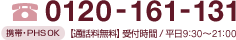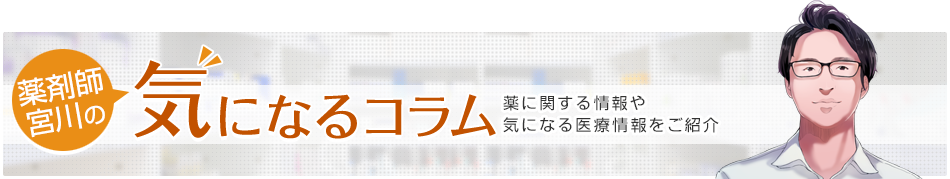国の政策もあり、ジェネリック医薬品に関しては、医療関係者以外の方でもよく耳にするようになり、認知度がかなり上がっています。一方、バイオシミラーに関してはまだまだ知られていないものになります。今回はこの違いについて見ていきたいと思います。
ジェネリック医薬品について再度復習してみよう!
ジェネリック医薬品は、日本名では「後発医薬品」と呼ばれ、以前は「ゾロ」などとも呼ばれていました。先発医薬品と比べると有効成分は同じで、添加物が違っているものとなります(添加物もまったく同じものもあり、オーソライズドジェネリック医薬品と呼ばれていますが、今回はこれを除きます)。
たまに医療関係者の中にも、患者さんに聞かれた際に、「先発品と同じですが、安い医薬品です」と説明している場合もありますが、厳密に言うと添加物が違うため、同じではありません。しかしながら、この「同じ」の部分が、どう同じなのかがポイントとなります。
また、バイオシミラーは、日本名では「バイオ後発品」と呼ばれ、名前の通り、「先行バイオ医薬品のジェネリック医薬品」ということになります。
2つの違いとは?
2つともジェネリック医薬品である以上は先発医薬品と同じであると思いがちですが、前述したように、「何がどのように同じなのか」を理解する必要があります。ジェネリック医薬品は先発医薬品と比べて、「有効成分、投与経路、用法用量、効能効果が同一」という特徴があります。裏を返せば、この「4つが同一です」という説明は、患者さんに説明する時には正解と言えます。ただし、添加物が違うため、副作用の出やすさ、アレルギーの有無など違ってくる部分もあります。
他方、バイオシミラーに関しては、先行バイオ医薬品と比べて、「品質、有効性、安全性が同等・同質」という特徴があります。何故同一性ではなく同等性・同質性が求められるのかというと、ジェネリック医薬品は化学合成で作られるものなので同一の分子構造を常に再現することができる一方、細胞培養技術を用いて作るバイオシミラーでは、分子構造がとても複雑となり、同一性を示すことが困難となるので、同等性・同質性を示すことができれば大丈夫ということです。
臨床試験においても違いがある?
ジェネリック医薬品の承認のための臨床試験は、すでに厳しい臨床試験を経て承認されている先発医薬品が存在しているため、比較的少ない試験で済む一方、バイオシミラーの場合にはそうはいきません。
前述したように、先行バイオ医薬品と同じ構造の成分を作ることが困難となるため、同等性・同質性を示すことになりますが、同一性が示せないまでも、やはり医薬品である以上、同一性に限りなく近い水準が求められることは否めません。
こういった事情から、バイオシミラーの臨床試験においては、通常のジェネリック医薬品の臨床試験よりも多くの試験が求められます。つまり、バイオシミラーを世に出そうとした際の負担は結構大きくなるため、なかなか爆発的にその数が増えていないというのが実情です。
そこまでしてバイオシミラーが必要とされる理由とは?
バイオ医薬品自体が、これまでの医薬品以上に、難治性の病気にも使えるという特性から、昨今話題の抗体医薬を含めて、今後も使用する患者数が増えてくることが予想されますが、製造コストがかなりかかるため、薬価がかなり高価なものとなります。このような中、やはり問題になってくるのは医療費の高騰問題です。特に税金が背景となっている国民皆保険制度を取っている日本においては財政圧迫につながるため深刻です。
そこで福音となるのがバイオシミラーです。バイオシミラーは後発品であるということは事実なので、薬価がかなり抑えられます。バイオシミラーは先行バイオ医薬品の7割くらいに薬価が抑えられるので有用です。
今後バイオシミラーの種類はどんどん増えてくることが予想されています。薬剤師であれば目にする機会も増えるのは確実なので、ぜひ自分でも勉強してみてください。
リクナビ薬剤師では働く薬剤師さんを応援しています。
転職についてお悩みの方は以下のボタンよりご相談ください。