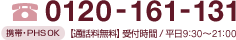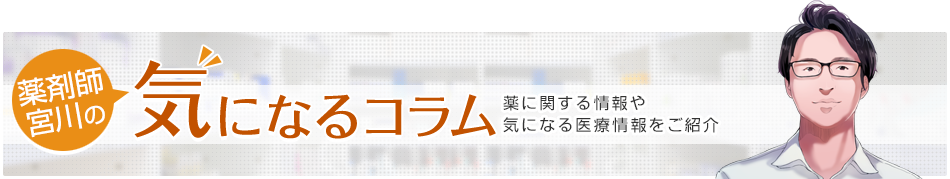超高齢社会、かつ、人生100年時代を迎えて、人生の最終段階において患者さん本人の意思に基づき、適切な医療を提供しようという流れがますます加速しています。以前のように病院のベッドでただ死を待つだけというのはもはや時代遅れと言えます。そのような場面で薬剤師の役割が期待されています。一緒に見ていきましょう。
ACPとはそもそもどんなもの?
医療従事者や介護従事者などの多職種連携の一環として、患者さん本人の意思決定を手助けできる集まりである「人生会議」のことをACP(Advance Care Planning)と呼びます。以前から構想自体はありましたが、最近になって活発に言われるようになりました。厚生労働省自体も積極的に普及活動を行っており、日本薬剤師会でもACPに関する薬剤師向けの研修を計画されています。誰にも必ずやってくる人生の最期をどうやって迎えたいか、また、それまでの間にどうやって自分らしく生活したいかなどについて、患者さんが決めることを適切に支援できるようにするというのがACPの趣旨です。
薬局薬剤師はACPには必要不可欠?
そもそもACPの認知度についてはまだ高いとは言い難い現状です。医師や看護師などではおよそ半分が知っているという現状のようですが、薬剤師に関してはあまり浸透していないというのが実情だと考えられています。病院薬剤師ならともかく、薬局薬剤師ではあまり関係ないと感じるという側面もあるかもしれませんが、実は、厚生労働省的には、むしろ病院薬剤師よりも薬局薬剤師にこそ、ACPに積極的に関わってほしいと考えているようです。
なぜかというと、薬局には高い地域性という特性があり、その地域特有の医療・介護事情を把握しやすい場所であるという理由があります。加えて、病院と異なり、薬局は、病気の方だけでなく、健康な状態の方もいらっしゃる場所であり、その健康な方が病気になった場合には、健康な状態からいろいろな情報を把握することが可能となる場所でもあるということもあります。病気になった後の情報以上に、病気になる前の情報というのはとても重要な側面があり、薬局薬剤師こそ、ACPの実践にはなくてはならない存在と言えるのではないでしょうか。
ACPにおいて薬剤師がやるべきことは?
人生の最期を考えると言っても難しく考える必要はありません。これまで薬剤師として当たり前のようにやってきたことが大きな武器になります。具体的には、末期がん患者さんにおける疼痛コントロール、経腸栄養管理、服用している薬の管理などになります。末期がんなどの終末期ケアにおいては、亡くなる直前まで薬を使用することが少なくなく、さらに不要な薬まで漫然と使用していることで、QOLが低下してしまっているという場面も結構見られますので、「最期まで自分らしく生きる」というスローガンを鑑みると、やはり薬剤師の関与が大事だと考えられます。
ACPと緩和ケアとは似て非なるもの?
ACPと緩和ケアは一見似ていますが、実は違う概念です。どちらも終末期に関係するという点では共通ですが、緩和ケアについては、苦痛を軽減してQOLを向上させるためのケア自体を指しますが、ACPは患者さん、ご家族、医療従事者などがチームで話し合い、将来的に患者さんの意思決定能力が低下した際にでも、患者さんの希望にそった医療ケアを提供できるように事前に決定しておく過程全般を指します。もちろん、共通した部分もあるので、両方の知識と技能を習得しておくことは大きなメリットになります。
ACPに関わっていくためには?
ここまで読んでいただいた中には、ACPに興味を持ったという方、または、もっと自分で勉強してみたいという方もいらっしゃると思います。まずは厚生労働省などが主催する勉強会などに参加されると良いでしょう。また、一般社団法人日本プライマリ・ケア連合学会をはじめ、各種学会も独自にACPに関連した勉強会やセミナーを企画しているのでそういったものにも参加してみると良いでしょう。
近年は、e-learningなどのオンラインのものも増えてきたので、仕事の休憩中といった状況や、どうしても子育てや介護で家を離れられないという方でも比較的参加しやすくなってきています。ぜひ一人でも多くの方が積極的にACPに関与してみてください。
リクナビ薬剤師では働く薬剤師さんを応援しています。
転職についてお悩みの方は以下のボタンよりご相談ください。