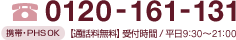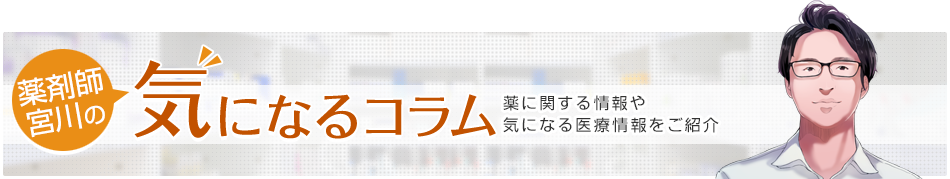国民の健康に直接的に関与している法律の一つである薬機法は、比較的改正の頻度が多いという特徴があります。時代に即した内容がスピーディーに盛り込まれてきました。今回の改正でも新しい概念が加えられました。今回は改正のポイントを一緒に見ていきたいと思います。
現在の薬機法はそもそもどんな法律?
正式名称としては、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」であり、医薬品のほかに、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品に関する規定を設けている法律になります。正式名称が長いため、医薬品医療機器等法や薬機法と略されます(本記事では薬機法で統一します)。以前は「薬事法」という名前でしたが、iPS細胞をはじめとした再生医療の重要性が増してきたことから、再生医療に関する規定が強化されて今の名前になりました。薬だけでなく、より幅広いものが規定されるようになったということです。
今回の改正のポイントは?
多くの方が理解していることかもしれませんが、コロナ禍前後で医療の在り方は大きく変わったと言えます。コロナ禍で生活様式が変化したことで、医療の在り方も変化してきました。コロナ禍の中で新しい医薬品やワクチンが活発に開発されていたというスピード感も印象的だったと思います。そういった背景から、次に挙げる事柄が改正のポイントとなります(ただし、多くの薬剤師に関係する内容だけに絞ります)。
(1)一部の調剤業務の外部委託解禁
(2)市販薬の新たな販売規制緩和と販売制限
(3)医薬品の安定供給対策
(4)創薬スタートアップ支援
大まかに言うと、前半2つは薬局薬剤師などに関係するもの、後半2つは製薬企業や研究所などに所属する薬剤師に関係するものとなります。
まずは前半2つに関して見てみよう!
それぞれをもっと詳しく見ていきましょう。
(1)に関しては、調剤業務のうち、医薬品のピッキング、包装、事務作業に関しては同じ都道府県内にある別の薬局に外部委託可能ということです。これはあくまで単純な対物業務に関しての規定で、服薬指導などの対人業務に関してはもちろん不可となります。これにより、薬剤師がもっと専門性の高い業務に集中できるようになることが期待できます。
(2)としては、薬剤師や登録販売者がいない店舗においても、販売店舗とは別の場所の店舗の薬剤師などがオンライン設備等を活用することで、販売店舗の市販薬を遠隔で管理して購入者へ販売することができるようになるということです(ただし、しばらくの間は、販売店舗と有資格者が所属する別の店舗とは同一都道府県にある場合に限ります)。加えて、これまで対面販売が原則だった要指導医薬品の一部についてのオンライン販売が解禁されました。
一方、近年社会問題となっているオーバードーズ対策として、「濫用等のおそれのある医薬品」については、20歳未満への販売時には、複数・大容量販売は禁止になり、かつ、購入者の使用状況確認と情報提供が義務づけられました。
後半2つに関しても長い目でみればかなり重要!
後半2つに関しては、未来に向かって重要な項目です。
(3)に関しては、昨今の供給問題対策として、安定供給の責任者として、製薬企業に「特定医薬品供給体制管理責任者」の設置を義務付けるというものです。医薬品を供給する企業自身でも供給体制をモニタリングすることが必須となったということです。
最後に(4)に関しては、新規医薬品が生まれにくくなった日本における状況を改善しようとするものです。国費だけでなく寄付金から運営される「革新的医薬品等実用化支援基金」を設置して、創薬に関わるスタートアップ企業を支援するという仕組みを作ったという規定です。
これは特に未来の医療をより良いものとするために重要な規定です。薬局などの現場にいる薬剤師にとっては身近ではないですが、未来の医薬品が今後日本から生まれていくことが期待されますので、ぜひ知っておいてほしい事柄です。研究者の私から見ても、日本でこういった基金ができるということは大変画期的だと感じています。
どの業種にいるとしても、薬剤師であれば常に最新の法改正情報には精通しておきたいものです。ぜひご自身でも勉強してみてください。
リクナビ薬剤師では働く薬剤師さんを応援しています。
転職についてお悩みの方は以下のボタンよりご相談ください。