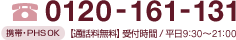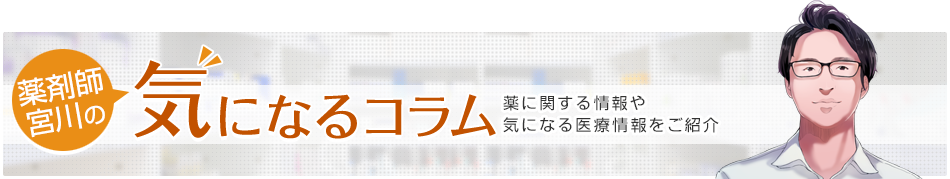日本の新年に昔から欠かすことができないものといえば、お屠蘇とおせち料理です。最近では一人暮らしの若者の増加や、高齢者同士が住んでいるお宅も増えてきたため、自作される方が少しずつ減少していっており、少し寂しいところです。
そんなお屠蘇とおせち料理ですが、実はただのお祝いのものではなく、そこには健康にまつわる話が隠れており、薬剤師であれば知っておくべきルーツがあったのです。今回はこちらを紹介します。
お屠蘇のルーツは薬酒だった?!
お屠蘇は独特の味のするお酒です。子どもの頃に周囲の大人が飲む際に漂うその独特の匂いを、思い出す方も多いのではないでしょうか。
「屠蘇」は本来、「悪い鬼を屠り、死んだ人を蘇らせる」という意味です。正式名称を「屠蘇延命散(屠蘇散)」といいます。様々な生薬の成分を日本酒やみりんで抽出し、その上澄み液を集めたものです。その歴史は古く、中国から遣唐使によって伝えられ、平安時代には宮中行事として正月に利用され始めたのがはじまりと言われています。その後庶民にも浸透し、病気や邪気を払い、長寿を願う儀式として定着しました。
昔は、病気は邪気のしわざと考えられていたので、お屠蘇により邪気を払うことで健康になっていると考えられていました。ですが、現代科学から見ても、生薬がたくさん入っていることを考えると、病気の予防として理にかなっている感じはしますね。
お屠蘇の中の生薬の種類は地方によって多少異なりますが、チンピ、ケイヒ、サンショウ、ダイオウ、ビャクジュツなどをベースとしています。配合されている生薬によって異なってきますが、効能は、健胃効果、吐き気止め、利尿効果、風邪予防、発汗促進、下痢止めなどと言われています。寒くて胃腸が弱っている中で、普段よりも食べ過ぎ飲みすぎになりがちな新年に飲むことは、健康増進という観点からも非常に効果的ですね。
おせち料理も薬膳料理だった?!
おせち料理は、お節句(せちく)料理が正式名称です。お正月のみならず、ひな祭りや端午の節句など、季節の節目に感謝の意をもって神様にお供えするものでした。といっても、神棚に特別に供えるというものではなく、供え物としてみんなで分け合って食べることで自身の健康増進とし、神様とも分け与えることで感謝の意としました。これは現代の日本のお祭りでも「神人共食」と呼ばれ、残っています。
そんなおせち料理ですが、旬のものを食べることで旬の生命力を体内へと注ぎ込むということが重んじられました。現代栄養学でも、旬のものは一番栄養素が高い状態だということがわかっていますので、古来の人々は感覚的に理解していたのだとすると、改めて日本人の知恵には感服させられます。つまりおせち料理は一番栄養素が高い旬のものを健康増進のために使った、薬膳料理だったとも言えるのです。
そんなおせち料理は、年に何回かある季節の変わり目の節句の中でも、特にお正月が一番大切と考えられるようになり、「正月料理」として定着していきました。
食材は、栗や数の子、黒豆、れんこん、ごぼうなどが使われており、それぞれに縁起が良い逸話が関係しているということは周知の事実かと思います。ですが、実は栄養学の観点からも、非常に栄養のバランスよく取れるように考えられていると言われています。
唯一の欠点といえば、冷たくなっている状態で食すので、体が冷えてしまうということです。ですが、この欠点はお雑煮を一緒に食べることで補っている訳です。さらにお雑煮に餅を使うことで、おせち料理にはなかった米の要素も取り入れられます。もちろん食べ過ぎるとよくないので、みんなで分け合えば一人当たりちょうどよい量を食べるようになっています。こちららも理にかなっていますね。
是非これからお正月におせち料理やお屠蘇を摂取する際には、薬膳を意識してみてください。